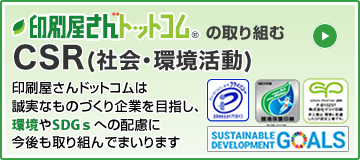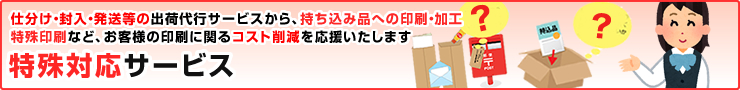SDGsという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
SDGsとは、社会全体で取り組んでいく新たな施策のことであり、そこには企業での働き方も含まれます。
そこで今回は、SDGsと働き方改革の関係についてご紹介します。
□SDGsについてご紹介!
SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略称であり、日本語ではよく「持続可能な開発目標」と訳されます。
2015年の国連サミットにおいて採択されたSDGsは、17のゴールと169のターゲットによって構成されています。
ゴールとは「貧困をなくそう」や「飢餓をゼロに」といった大きな目標のことであり、ターゲットとはゴールを達成するために何をするのかを定めたものです。
例えば、「飢餓をゼロに」といったゴールに対しては、「2030年までに飢餓を撲滅する」や「2030年までに若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う」といったものがあります。
1つのゴールに対し複数のターゲットが設定されており、これらのターゲットは幅広い分野で定められていることが特徴的です。
□SDGsと働き方改革との関係
ここまではSDGsとはなにかについてお伝えしましたが、ではSDGsと働き方はどのような関係にあるのでしょうか。
ここではSDGsと特に関係の深い3つのゴールをご紹介します。
*すべての人に健康と福祉を
このゴールは誰もが健康でいられるために福祉の充実性を高めることを目標にしています。
近年は長時間労働や育児・介護の人手不足が問題視されています。
長時間労働の改善や育児・介護をするための休暇取得促進、ルールの整備などは、すべての人の健康を守るために企業が行える取り組みだといえるでしょう。
*ジェンダー平等を実現しよう
近年は女性の社会進出といった言葉を耳にすることが多くなってきたかと思いますが、それでも日本は男女格差が大きい国として知られています。
特に、管理職の男女比は欧米諸国と比較すると、非常に低いためその格差が問題視されています。
この問題は国や企業の体制・制度によって解決が見込まれるため、これらの整備は非常に重要なポイントです。
*働きがいも 経済成長も
誰もが十分な賃金をもらえて、働ける社会をゴールとするこの目標は働き方改革と深い関係にあります。
働き方改革では長時間労働の解消や同一労働同一賃金といった取り組みを行っており、これらを実行することはこのゴールの達成につながります。
□まとめ
今回は、SDGsと働き方改革の関係について紹介しました。
SDGsとは17のゴールと169のターゲットによって構成されており、これらには多くの分野が関係しています。
働き方改革を進めることはSDGs達成につながるため、非常に大切な取り組みだといえるでしょう。