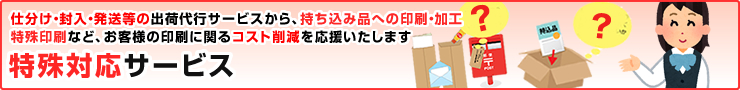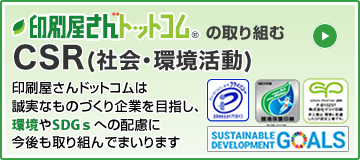2015年9月、国連総会は2030年までに達成すべき17の目標「持続可能な開発目標」(SDGs)を採択しました。その中で、2番目の目標に「飢餓をゼロ」が定められました。
そこで今回は餓死問題解決策と私たちにできることを紹介します。
□餓死問題に対するSDGsの解決策とは?
「飢餓をゼロ」を達成するための方法を3つ紹介します。
1.「飢餓をゼロ」
世界中には最も貧しい生活を送る20億人の支援が必要であり、彼らの生活を変えるためにも積極的な援助が求められています。
生命の救済だけでなく、自立を促進し購買力を向上させる社会保障政策に注力することは重要で、これにより、新たな需要と雇用が生まれ、地域経済の活性化につながるでしょう。
2.食料廃棄・ロスの削減
世界中には、十分な食料があり、すべての人が飢えることなく食べられる可能性があるのですが、年間に生産される40億トンの食料のうち、約3分の1が無駄になっています。
この食品ロスによる経済損失は年間で約7,500億ドルに上り、先進国では主に消費段階での廃棄が問題となっていますが、途上国では貯蔵設備の不備や農家の市場へのアクセスの制約などが原因で、収穫された作物が無駄になってしまっているのが現状です。
3.栄養改善を優先課題に
子どもや妊娠中、授乳中の母親が健康的な成長を促進するためには、適切な栄養摂取が重要です。
そのためにもバランスの取れた食事を通じて必要な栄養素を十分に摂取できるよう、支援が大切です。
□私たちが出来ることは?
「飢餓をゼロ」を達成するために私たちができることを紹介します。
*国産のものを購入
第一に、国内での食材の購入が挙げられます。
各国が自給自足の食料を確保できるようになることは、飢餓問題を解決するための近道となります。
日本は輸入に依存していることが一般的に知られています。
消費者として、国産の食材を選ぶことは、食料の自給率を高めるだけでなく、国内の農家をサポートすることにもつながります。
また、国内産の食品は輸送距離が短いため新鮮であり、環境にも負荷をかけず、SDGsにも貢献できます。
*食品ロスを減らす
食品ロスの削減も非常に重要な取り組みです。
2020年、日本では約522万トンの食品ロスが発生し、そのう、事業者による食品ロスは275万トン、家庭からのロスは247万トンでした。
消費者庁は、食品ロスの削減には事業者と消費者の協力が欠かせないと呼びかけています。
□まとめ
今回は餓死問題解決策と私たちにできることを紹介しました。
「飢餓をゼロ」は飢餓を終わらせ、食糧の安定・改善をめざしたもものになっています。
飢餓の問題を改善するために、今回紹介した自身でできることをやってみてください。