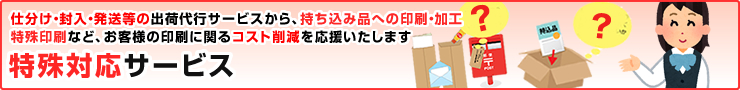SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」には、食料の損失削減を目指す項目が提示されています。
上記の項目とフードロスという社会問題は密接に関係しており、目標達成のためには私たち一人ひとりがフードロスの現状を理解する必要があります。
今回は、世界や日本のフードロスの現状と、私たちが日常でできることをご紹介します。
□世界と日本のフードロスの現状
SDGsで一気に話題になった言葉、フードロス。
フードロスとは、本来まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。
世界各地でさまざまな事情により食品が廃棄されていますが、その量は「人の消費のために生産された食料の約3分の1」にも上ります。
その量実に13億トンと、想像を絶する量の食料が無駄になっているのです。
日本でもフードロスの深刻さが問題になっています。
日本で発生している食品ロスは、2016年で643万トン、現在も減少傾向にはあるものの大量の食料が廃棄されている現状は変わりません。
日本人1人当たりでは年間50キログラム、1日茶碗一杯分の食料を廃棄していることになります。
フードロスは、飲食店や小売業などで発生する事業系廃棄物と、各一般家庭から出る家庭系廃棄物に分けられ、廃棄の割合はちょうど半分ずつ程度です。
飲食店からの廃棄ばかりだと思われている方も多いかもしれませんが、私たちが普段出しているフードロスも無関係ではないのです。
□食べ物を無駄にしないために私たちにできること
では、フードロスのために私たちに一体何ができるのでしょうか。
身近にできることをご紹介するので、ぜひ意識して取り組んでみてください。
*買い物の前に冷蔵庫を確認する
食料を買い込みすぎて余らせてしまい、気づいたら冷蔵庫で腐っていたという経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
普段から冷蔵庫の中身を把握することは難しくても、買い物前に一度冷蔵庫の中を覗くことで今必要な食料だけを買う習慣を身に付けましょう。
*手前どりを意識する
すぐに消費するものであれば、賞味期限はまったく問題ないはずです。
お店の商品は基本的に賞味期限の近いものが手前に並んでいるので、賞味期限の近い手前から取る「手前どり」を心掛けてみてください。
*適切な保存方法を知る
食料の適切な保存方法を知っておけば、普段の保存方法より長く美味しく保存できることがあります。
傷んでしまう食料を少しでも減らすために、最適な保存方法を知っておきましょう。
□まとめ
フードロスは、将来の食料危機を見据えて今取り組んでおくべき非常に重要な問題です。
日本で、まだ食べられる食料が年間600万トンも捨てられていること、その半分は私たちが出す家庭ごみの中にあることを知って、フードロス削減を意識することが大切です。
買い物前に冷蔵庫を見る、手前どりを意識する、適切な保存方法を知る。
この3つを日常に取り込むことが、フードロス削減の第一歩です。