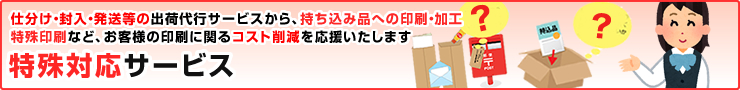フードロスという言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
日本では食品ロスと呼ばれる方が耳馴染みがあるかもしれませんが、いずれにせよフードロスは世界で話題になっている社会問題の1つです。
SDGsでも「12.つくる責任、つかう責任」という目標の中にフードロス削減が掲げられています。
そこで今回は、フードロスについて私たちが身近にできることをご紹介します。
□フードロスの現状
フードロスとは、まだ食べられるはずの食品が大量に廃棄されている社会問題です。
2017年に農林水産省・環境省が行った調査では、世界で年間およそ13億トン、日本でも年間612万トンの食品が廃棄されています。
世界の廃棄量である13億トンは、世界で生産される食糧の3分の1の量にあたります。
さらに日本で廃棄される612万トンは東京ドーム5つ分と同等であり、日本人1人当たりお茶碗1杯分の食糧が毎日廃棄されていることになります。
対して世界中では、未だ約8億人が栄養不足や食料不足に悩まされており、このフードロスは世界中で解決すべき喫緊の課題になっているのです。
□フードロス削減のために私たちにできること
フードロスにおいて、家庭から廃棄されている食品が占める割合は47%と意外に高く、飲食店からの廃棄だけがフードロスの原因でないことは明らかです。
フードロス削減のためには、私たち一人ひとりがフードロスのためにできることを探すことが大切なのです。
*買い物の前に冷蔵庫を確認する
家にあったものをまた買ってしまうと、消費が追いつかなくなりフードロスが発生しやすくなります。
買い物前には、家に何が残っていて何が足りないのか、しっかり確認しておきましょう。
*手前どり
手前どりとは、すぐに食べるものであれば賞味期限が近い商品棚の手前から商品を取っていくようにしよう、という心がけのことです。
飲食店で提供している食品は消費期限が切れると廃棄されますが、できるだけ消費期限の近いものを選ぶことで、廃棄削減に貢献できます。
*過剰除去を減らす
実は食べられる皮や茎、葉などの部分を過剰に除去することを、過剰除去と言います。
特に野菜は過剰除去が多いので、少しでも食べられる部分を捨てないように意識することが大切です。
□まとめ
まだ食べられるはずの食品を廃棄するフードロス問題は、先進国で特に課題とされており、日本も例外ではありません。
毎日1人茶碗1杯分の食品が廃棄されている現実は、決して目を背けてはいけない社会問題です。
私たちが今日からできることとして、買い物の前に冷蔵庫を確認すること、手前どりを意識すること、過剰除去を減らすことが挙げられます。
ぜひ意識して、フードロス削減を達成しましょう。