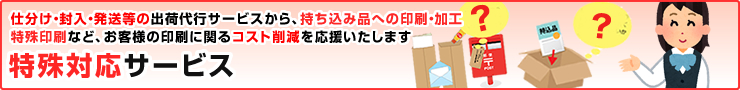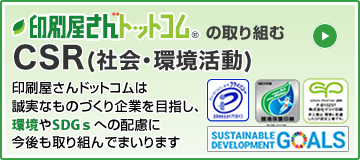ノベルティとは企業が宣伝目的で無料配布する商品のことで、ノベルティを作る上ではどのような商品を選ぶかという点が重要です。
カレンダーや文房具などさまざまな種類がありますが、今回はノベルティにタンブラーをおすすめする理由についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□ノベルティにはタンブラーがおすすめ!
タンブラーをおすすめする理由は、実用性が高いからです。
ノベルティは企業の宣伝目的で配布するものであり、その商品の使用頻度が多いほどその宣伝効果は高まります。
使用頻度はノベルティの使いやすさや実用性によって変わり、気軽に使えて携帯できるタンブラーはノベルティに適している商品だといえます。
また、タンブラーをお店で購入しようとすると、数千円するものが多いため、そのタンブラーが無料でもらえるのであれば嬉しいと感じる人も多く、そのノベルティを使用してくれる機会も多くなるでしょう。
そして、タンブラーは家でも外出先でも使用できます。
お店によってはタンブラーを持参して、そこにコーヒーを入れてもらうことによって、割引になるといったコーヒーショップもあります。
これはタンブラーを使用することで、プラスチックの容器を使用しなくて済むからです。
このようにタンブラーは環境にもお財布にもやさしいことから、ますます人気が高まっていくと考えられるため、ノベルティとしておすすめです。
□ステンレスタンブラーの魅力!
*保温・保湿効果
ステンレスタンブラーには保温・保湿効果があり、持つ部分は中の飲み物の温度によって変化せず、水滴がつかないといった特徴があります。
この効果はステンレスタンブラーの構造によって生み出されています。
ステンレスタンブラーの構造には2種類あります。
1.ステンレス製真空二重構造
これはステンレスの二重構造の内側と外側の間が真空になっている構造です。
真空になっていることによって、内側と外側の両側からの熱が伝わらないため、高い保温・保冷効果を生み出せます。
このような構造は、中の飲み物の温度に関係なくタンブラーの温度は変化せず、水滴がつかないといったメリットを生み出しています。
2.ステンレス製二重構造
これはステンレスの二重構造の内側と外側の間に空気層がある構造です。
真空ではないため、保温・保冷効果がやや低めになってしまいますが、その分安く購入できるといったメリットがあります。
□まとめ
今回は、ノベルティにタンブラーをおすすめする理由について紹介しました。
タンブラーは実用性が高いため、ノベルティとして喜ばれます。
タンブラーといってもその構造によって性能や魅力が変わるので、これらを考慮して選んでみてください。