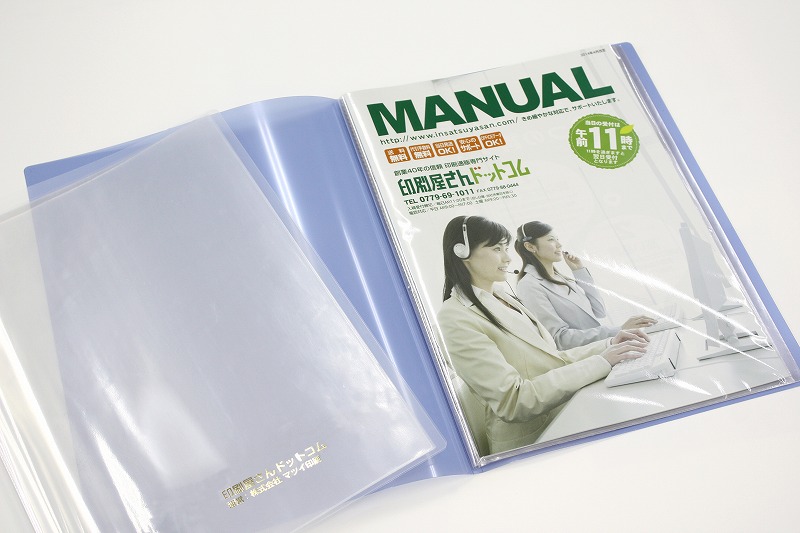卒業式やスポーツ少年団の卒業式などで、どんなプレゼントを贈ろうかとお悩みの方はいらっしゃいませんか?
プレゼントは人数分用意しないといけないので、子供たちの個性をすべて考慮して一つのプレゼントに決めるのは大変ですよね。
そんなプレゼント選びにお悩みのあなたに、印刷屋さんドットコムがオススメしたいのは「オリジナルデザインがプリントされている定規」です!
「でも私たちの団体で定規をプレゼントしても喜ばれるのかな…?」
と不安になっているそんなあなたのために、今回はプレゼントで定規が贈られているのはどんな時なのか、その事例をご紹介していきます!
〇小学校や中学校の卒業式
プレゼントに定規が贈られる機会としては、小学校や中学校の卒業式が挙げられます。
定規にプリントするデザインはイラストを描いてもらっても、写真を印刷するという方法でも構いません。
小学校・中学校の卒業式であれば、学校のエンブレムをイラストとして描いてみたり、少人数のクラスでしたら、クラスメイトの似顔絵を描いてみたりするのはいかがでしょうか?
小学生・中学生にとって、定規は実用品としても役立ちますし、アルバムなどの思い出としての役割も果たしてくれるため、お子様たちに気に入ってもらえることでしょう。
〇地域のスポーツチームの卒団式
また、オリジナルの定規を贈るのは、何も小学校や中学校の卒業式だけではありません。
ご利用される方に多いのが、地域のスポーツチームの卒団式の思い出の品です。
チームメイトの人数でしたら、小学校の1学年よりは人数も少ないと思いますので、全員の集合写真を印刷するというのはいかがでしょうか?
絵の上手な人がいれば、全員の似顔絵を描いてみても楽しそうではないでしょうか。
〇自分、もしくは友達に向けて
オリジナルの定規をプレゼントする対象は、学校関連の人だけではありません。
お友達用・私用でもお作りすることができます。
ちなみに印刷屋さんドットコムでは1個~500個の定規を作ることが可能です!
市販の定規ではなくて自分でデザインを考案したいという場合には、ぜひご利用になってみてはいかがでしょうか。
今回は記念品として贈りたい定規をご紹介しました。
印刷屋さんドットコムでは、お客様がお選びになったデザインを15cm定規に印刷して、オリジナルの定規を作ることができます。
また、デザインをお考えの際に、白打ちを入れるか入れないかを選んでもらうことができます。
白打ちありにすると、デザインがくっきりと見えますし、この白打ちをなしにすることでデザインに透明感を持たせることができますよ。
贈り物としてオリジナルの定規を贈ることをお考えの際には、ぜひ印刷屋さんドットコムをご利用くださいませ。