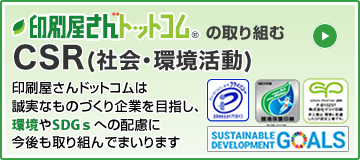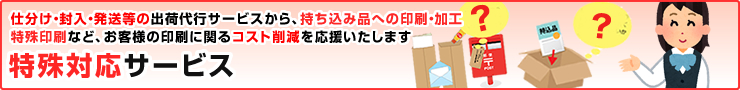近年、SDGsという言葉を耳にします。
今や経済活動を行うにあたって、SDGsは切っても切れない関係にあります。
そして、SDGsと似たものに社会貢献という言葉があります。
そこで今回は、SDGsと社会貢献の違いと、SDGsに取り組むメリットについて紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□SDGsと社会貢献の違いとは?
まず、SDGsとは、世界が抱える問題を解決するために国連で採択された「持続可能な開発目標」のことです。
そして、SDGsが広く認知される前は社会貢献に取り組むことが一般的でした。
社会貢献とは、CSRとも呼ばれ、企業が従業員や消費者などから信頼を得るために行う慈善活動のことを指します。
これは、信頼を得るための取り組みを行うことで、結果として社会貢献につながるというものです。
このように、SDGsと社会貢献は似ているように見えますが、1つ決定的な違いがあります。
それは、社会貢献があくまでもボランティアなのに対して、SDGsはビジネスを用いて社会を良くしようとしている点です。
SDGsの大きな特徴は、さまざまな問題の解決に用いられる力がそのままイノベーションにつながることです。
そのため、SDGsでは「より良い社会をつくる」と「ビジネス」の2つの概念が両立しているのです。
□SDGsに取り組むメリットをご紹介!
以下より、SDGsに取り組むメリットを紹介します。
1つ目は、新しいビジネスの機会が生まれることです。
SDGsは、17の目標と、さらにその目標に対して169のターゲットが設定されています。
これらの目標を解決するためにさまざまな取り組みを行うことは、新しいビジネスチャンスの発生が期待できます。
2つ目は、コストが削減できることです。
SDGsの目標の中には、環境に配慮されたものも含まれています。
そのため、省エネや省資源対策に取り組む場合が多いです。
つまり、普段使用するエネルギーがクリーンに、そして量が減ることでコスト削減につながるのです。
3つ目は、世間のイメージが向上することです。
SDGsでは、世界規模で解決を目指すような目標が決められています。
そのため、こうした課題に積極的に取り組むことで、世間から評価されてイメージ向上にもつながります。
□まとめ
今回は、SDGsと社会貢献の違いと、SDGsに取り組むメリットについて紹介しました。
SDGsと社会貢献は似ていますが、ビジネスが絡んでくるのがSDGsです。
この記事が皆様のお役に立てば幸いです。